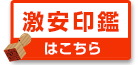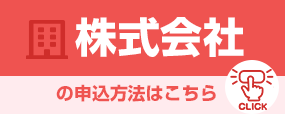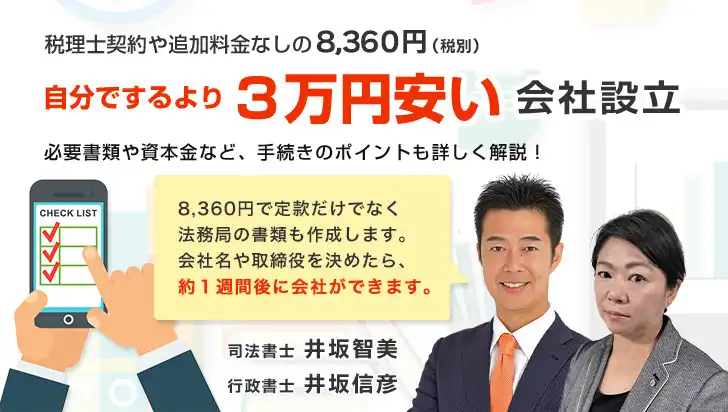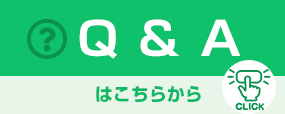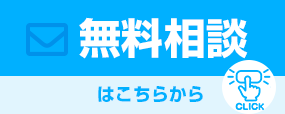マイクロ法人の設立を考えているけれど、何から始めれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
設立や会社の形態を決め、事業を継続させる際には自分の希望や考え方、設立後の展望に合った形態を選ぶことが非常に重要です。また、法人設立のメリットやデメリットを踏まえた上で個人事業主と法人設立のどちらが自身の事業体に合っているかを慎重に検討しなくてはなりません。それは、事業の将来性を含め、今後どのような事業体でありたいかも含めて熟慮すべきといえます。
本記事では、マイクロ法人の基本情報や設立のメリット、デメリット、設立の手順などを具体的に解説します。法人設立にあたり、思案中の方はぜひ参考にしてください。
マイクロ法人とは?
ここでは、マイクロ法人の基礎知識についてご紹介します。マイクロ法人の基本的な考え方や業務体系の特徴などを捉え、法人設立のメリットやデメリットまでしっかり抑えましょう。これらの項目をしっかり押さえることで、手続きをスムーズに執り行うことができるようになります。
1.マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、一言でいうと「代表者自身が一人で事業を行う事業形態」です。個人事業主から法人化することで、主に社会保険料や所得税の節税を目的として設立されることが多いとされています。
2.一般的な法人との違い
では、一般的な法人との違いはどのようなところにあるのでしょうか。ポイントとしては、事業拡大を目的にしているかどうかが大きな違いと言えるでしょう。一般的な法人は、雇用を行い、事業拡大をはかり、利益の維持をしながら株主に配当を行います。
しかし、マイクロ法人は自分以外の株主や役員は置かず、一人でできる範囲で事業を行います。つまり、従業員がいるかどうかという点でも違いがあります。
3.マイクロ法人と個人事業主の違い
次に、マイクロ法人と個人事業主の違いについてです。それは「法人格があるかどうか」という点です。
法人化をすることで、税務上のメリットを受けることができるため、節税効果を得るために、法人化を目指す方がいるのが現状です。
個人事業主であれば、開業届を税務署に提出するだけで簡単に起業できます。しかし、マイクロ法人を設立するとなると、法務局で法人登録を行うなど細かな手続きが必要になります。マイクロ法人を設立すべきか、個人事業主のまま事業を継続するかは、売上や収益に応じて、どちらがご自身にとってより良いかを検討してみましょう。
マイクロ法人を設立するメリットとデメリット
事業を展開する上で、売上や働き方、取引先などの事情により、個人事業主でいるべきか、法人化するべきか岐路に立つことがあるでしょう。その際には、メリットとデメリットを比較しながら検討してみましょう。
・メリット
① 社会保険料や所得税などが個人事業主より抑えられる
社会保険料や所得税などの納税を個人事業主よりも抑えることが可能です。
マイクロ法人を設立することで、法人から自分に対して「役員報酬」を支払うことができます。役員報酬を月額45,000円以下に設定すると、年間で最低550,000円の給与所得控除を受けることが可能です。法人の所得には個人の所得税よりも税率の低い法人税が適用されるため、結果として所得税と住民税の負担を抑えられる可能性があります。
② 経費として扱える幅が広がる
マイクロ法人は、個人事業主よりも経費として扱える範囲が広がります。一例として、役員報酬や退職金、会社運営にかかるオフィス賃料、、車両関連の費用(自動車保険なども含む)、出張手当、生命保険の一部などです。
ただし、必要以上に事業に関連しない費用を計上すると、後日課税される可能性もありますので、勘定科目には注意して対応しましょう。
③ 社会的な信用度が高くなる
事業を行う際には、個人的な信用はもちろんのこと、社会的な信用も仕事の有無に大きく関係します。
先述したように、マイクロ法人を設立するには、法人登録や定款の設定などの正式な手順を踏むことが必要です。その手順を経て「法人」という格がつくことにより、社会的な信用が高まります。その信用が高まることで、たとえば資金調達が必要な時に金融機関からの融資を受けやすくなることや、法人とのみ取引可能な企業とビジネスをするチャンスも生まれます。
また、マイクロ法人はすでに法人化されているため、役員を迎え入れることも可能であり、従業員を雇用し、取引からさらなる取引を展開したり、現在の事業の専門性を高めたり、別事業への展開など様々な可能性が広がります。
今後の事業展開などを考慮した上で、将来的に仕事の幅を広げたいと考えている場合には、マイクロ法人として仕事や取引を広げておくことも必要でしょう。
④ 事業継承や譲渡がしやすくなる
近年、人材や後継者不足は社会的問題となっています。2023年5月に公示された「全国新設法人動向調査」によると、2023年の「後継者不在率」は61.09%に上り、初めて60%を超えたという結果が出ています。後継者不在率が最も多いのは「建設業」となり全体の6割を占めています。建設業は、個人親方や個人事業主であることが多いのも一因と言われています。法人のみならず、事業継承がうまく進まず廃業の危機にある、または廃業となるケースが多いのも現状です。
マイクロ法人は法人そのものが契約主体となるため、代表者が交代しても法人は存続します。
例えば、株式や持分を譲渡することで、比較的簡単に経営者を交代します。
このように、個人事業主ではなく、マイクロ法人としておくことで、事業継承や譲渡を簡素化可能です。
【参考】「後継者不在率」が初の60%超え 円滑な廃業実務の見直しも必要
・デメリット
① 法人設立の手続き費用がかかる
先述したように、法人になるためには法務局での手続きなど、法的な手続きをとっている事業体です。そのため、手続きや設立、継続的なランニングコストなど、個人事業主では負担することがない費用が発生します。
<設立費用>
- ・株式会社:30万円程度
- ・合同会社:10万円程度
<維持費>
- ・法人住民税:7万円(最低額)
さらに、税理士に経理、決算などの委託などをする場合は、契約の方法にもよりますが、売り上げに応じた費用が発生します。節税を目的とした、マイクロ法人の設立の場合は、設立の費用やランニングコストが売り上げを上回らないかなど確認した上で検討をしましょう。
【参考】確定申告の基礎知識
② 赤字であっても法人住民税が発生する
ここで、個人事業主と、法人が納めるべき税金をわかりやすくまとめてみます。
個人事業主が納める税金:所得税・個人事業税・住民税・復興特別所得税
法人が納める税金:法人税・法人事業税・法人住民税・特別法人事業税
共通の税金:消費税・固定資産税・自動車税
法人が支払う「法人住民税」とは、「都道府県民税」と「市町村民税」があり、これらを合わせた税金のことです。事業所のある「地方自治体」に対して法人が納める地方税のため、「法人住民税」と呼ばれています。さらに法人が支払うべき税金には、「法人住民税」の他に「法人税」や「法人事業税」などがあり、それらをまとめて「法人税等」と呼ばれています。
ここで考慮すべきは納税額です。所得税と法人税の違いは、税率や控除額が違います。
| 課税所得 | 所得税率 | 法人税率 |
|---|---|---|
| 180万円 | 5% | 15% |
| 1,000万円 | 33%(実効税率:約17.64%) | 11.5%(800万円以下)+23.2%(800万円超) →実質約16.6% |
このように所得が一定の額を超えてくると、法人税の方が税率が低くなることがわかります。しかし、事業が上手く進まず赤字の場合であっても法人住民税を納めなくてはならないため、ここは大きなデメリットとして、法人設立の検討の材料になるでしょう。
③ 税務申告の手続きが複雑になる
マイクロ法人の場合、通常の法人と変わらない規模の決算報告を行う必要があり、個人事業主の確定申告よりも手続きが複雑になります。作成しなければならない書類がかなり多くなり、最初のうちは慣れるのに時間がかかることや、理解できないことも増えることでしょう。
そのため、法人になった場合には、税理士と顧問契約を結んだうえで決算申告手続きを行うことが一般的です。つまりは、税理士への顧問料や決算申告のための費用がかかることを考えると、費用負担という点でデメリットといえるでしょう。
しかも、決算などを期限内に終えることができなかった場合や不備があった場合は、延滞税やペナルティを課せられるなど、さらに深刻な事態になりますので、顧問料などはリスク回避としての必要経費であると考えましょう。
④ 報酬を支払うと社会保険の加入が必要になる
先述したように、マイクロ法人を設立した場合に、法人からの役員報酬にすることで社会保険料などの節税対策で恩恵を受けることができます。しかし、その前に社会保険の手続きを行う必要があり、社会保険の加入手続きの相場は一人につき、1万円〜2万円の毎月の費用、また初期費用もかかります。
節税の恩恵を受けることができるかどうかは、利益次第となります。スタートアップ時に初期投資としてまとまったお金が必要になるという面はしっかり頭に入れておきましょう。
⑤ 法人口座の開設が難しい場合がある
法人口座の開設には審査が必要になります。そこで場合によっては、法人口座の開設が難しいケースがあります。それは、近年増加している、実態のない会社などによる犯罪や不正防止の観点から口座開設を断られる可能性があるためです。
特に立ち上げ時、事業内容や目的が不明瞭であったり、主となる事業の許認可を得ていない場合や資本金が少額であったりすると審査が通らないことがあります。また、近年のIT化の波に乗りホームページは会社の顔、名刺代わりと言っても過言ではありません。ホームページや固定電話がない、バーチャルオフィスを利用しているなどの場合、法人としての信用が低くなり得ます。
マイクロ法人として法人化した場合は、法人口座の有無も信用のひとつとなりますので、開設ができるように、揃えるべきものは揃える必要があります。
マイクロ法人を設立する際の手順

ここまでのおさらいですが、マイクロ法人とは、会社を創業した代表者が一人で運営する法人を指しており、節税などにメリットがあるとされています。
では、このマイクロ法人を設立するにはどういった手順が必要なのかを見ていきましょう。
1.会社形態や設立するマイクロ法人の基本事項を決定する
法人設立には法に基づいた手続きを行う必要があります。設立に必要な基本事項には、以下のようなものがあります
- ・会社形態(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)
- ・会社名(商号)
- ・事業目的
- ・本店所在地
- ・資本金
- ・会社設立日
- ・役員 / 株主構成
2.法人用の実印を作成する
法人設立に必要な印鑑は、代表者印(実印)、銀行印、角印の3種類です。書類によっては捺印を求められるため、あらかじめ準備しておきましょう。
3.定款を作成し、認証を受ける
定款は法人のルールを定めたもので、公証役場での認証が必要です。紙で提出する場合は印紙代が発生しますが、電子定款では不要になります。
4.出資金(資本金)を振り込む
法人名義の口座がまだ存在しないため、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。この記録は後に払込証明書として提出されます。
5.登記申請書類を作成する
法人登記申請書類は法務局のサイトからダウンロード可能です。添付書類には以下が含まれます
- 定款(謄本)
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人決定書
- 役員就任承諾書
- 印鑑証明書
- 出資金払込証明書
- 印鑑届書
6.法務局で申請する
管轄の法務局へ登記書類を提出します。郵送やオンライン申請も可能ですが、初めてであれば窓口申請が安心です。
7.法人設立後に必要な手続き
設立後も各種届け出が必要です:
- 税務署(法人設立届出書など)
- 年金事務所(健康保険・厚生年金の手続き)
- ハローワーク(雇用保険関連)
マイクロ法人を設立する際の注意点とは?
1. 手続きの費用
株式会社では約30万円、合同会社では約10万円の初期費用が必要です。その他、毎月の社会保険料や税理士への費用、オフィス賃料などのランニングコストもかかります。
2. 法人の維持管理費
法人住民税は赤字でも最低7万円が発生します。その他にも税理士費用や経理作業など、維持のためのコストが個人事業主よりも高くなる可能性があります。
3. 税務署への対応
法人を立ち上げたばかりの段階では、税務署の信用が低いため、書類の不備などがあると調査対象となる可能性があります。専門家に相談するのもひとつの手です。
4. 必ずしも節税にはならないことへの理解
法人化すれば節税になるとは限りません。設立・運営コストや税率の違いなども含め、個人事業主の方が有利な場合もあるため、しっかりとした検討が必要です。
まとめ
マイクロ法人は、個人事業主から法人への移行を考える方にとって魅力的な選択肢です。しかし、設立や維持に費用がかかり、手続きも煩雑になるため、慎重な準備が求められます。法人としての信頼を得て事業を広げていくには、制度の理解と適切な対応が不可欠です。
本記事の内容を参考に、あなたのビジネスの次のステップへと繋がる確実な準備を進めていきましょう。