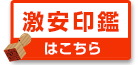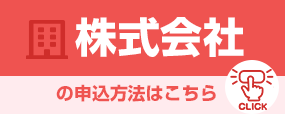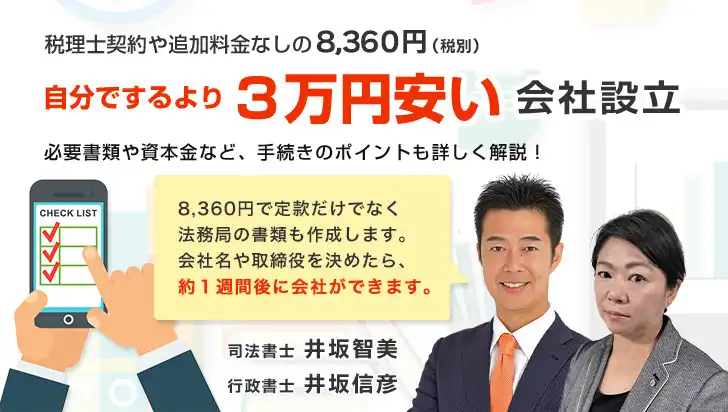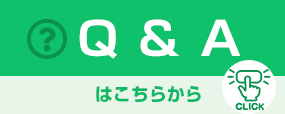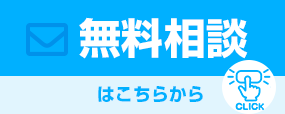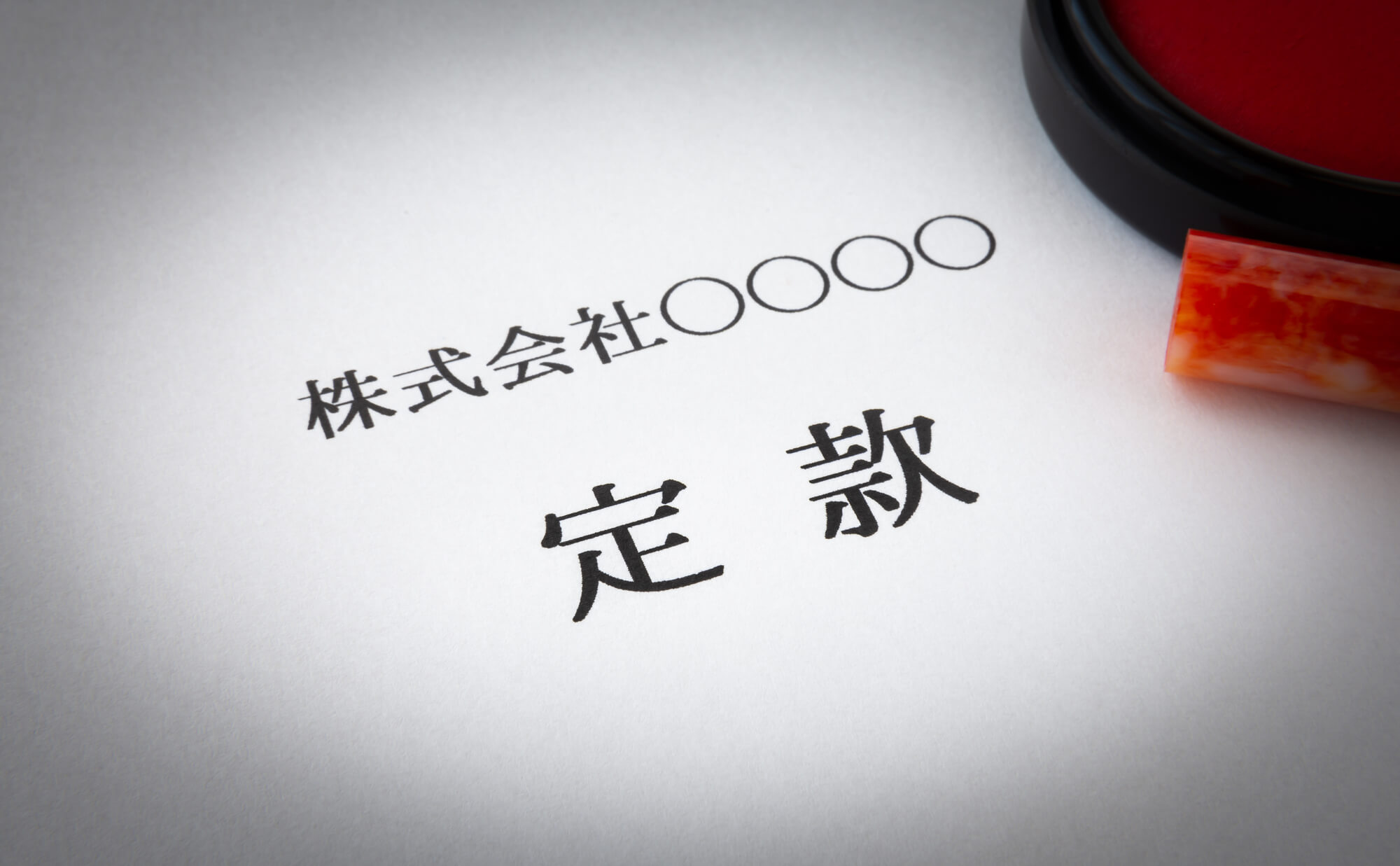
「会社を設立したけど、事業内容が変わってきたから定款を変更したい」「従業員が増えたので組織形態を変えたい」など、会社経営をしていると、定款を変更したいという場面に直面することがあるでしょう。
しかし、定款変更は、会社の根幹に関わる重要な手続きであり、その費用や注意点、手続きの流れなど、多くの疑問が浮かぶのではないでしょうか。
「定款変更って、一体どんな手続きが必要なの?」「費用はどれくらいかかるの?」「何か注意すべき点はあるの?」このような疑問をお持ちの経営者や担当者の方に向けて、本記事では、定款変更の手続きを徹底解説します。
現在、変更するのに何から始めるべきか迷っている、どんな手続きをすべきか検索している担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
定款変更の流れ
定款を変更する際には、いくつかの段階を経る必要があります。ここでは、その具体的な流れについて解説していきます。
まず、変更したい内容について株主総会で慎重に審議され、特別決議によって決定されます。その後、その決議内容を明確に記録した議事録を作成することが重要です。そして、決定された内容を法的に有効とするために、法務局で定款変更の登記申請を行います。最後に、変更後の定款は、会社の根幹となる原始定款と併せて適切に保管することが求められます。これらのステップを一つずつ見ていきましょう。
1. 株主総会の特別決議により定款変更内容について決議する
会社の基本的なルールを定めた「定款」を変更するには、株主総会で特別な多数決を行う必要があります。これが「特別決議」と呼ばれるものです。
通常の決議での多数決よりも厳しい条件があり、議決権を持つ株主の過半数が出席し、さらに出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成がなければ、定款の変更は認められません。
このような厳格な手続きが求められるのは、定款が会社の組織や運営、事業の目的など、会社の根幹に関わる重要な決定事項をまとめたものだからです。
一部の株主の意見だけで簡単に変更できてしまうと、ほかの株主にとって不利益が生じる可能性があるため、多くの株主の意思を反映させる必要があります。
株主総会では、変更案の内容が具体的に説明され、株主は質問をすることで内容を確認し納得した上で決定ができます。そして、それぞれの株主が会社の将来を考えて議決権を行使することで、会社の主軸となる重要な決定がなされます。
2. 株主総会の議事録を作成する
株主総会で定款の変更について話し合い、特別決議で賛成多数となったら、その内容を正式な記録として残す必要があります。
どのような議題について、どのような話し合いが行われ、どのような結論になったのかを証明する、非常に重要な書類となります。
議事録には、開催された日時や場所、出席した株主の数、議決権の数、そして議事の経過とその結果に基づいて、今回の場合は定款変更が承認されたことなどを具体的に記載します。そして、作成された議事録には、議長を務めた代表取締役などの役員と出席した取締役が署名します。
この株主総会議事録は、定款変更の手続きで法務局への登記申請を行う際に添付書類として必要になります。また、会社内でも重要な記録として保管され、会社の透明性を保ち、後々のトラブルを防ぐために大きな役割を果たします。
株主総会の議事録の保管期間は株主総会の日から10年、支店では議事録の写しを5年間保存する必要がありますので、保存期間も分かるようにしておくとよいでしょう。
3. 定款変更登記(法務局)
定款の変更が決まった場合、その内容を法務局で登記する必要があります。定款の内容を、国が管理する公式な記録に残す手続きとなります。
主に、会社の基本情報を変更する際には、法務局への変更登録が必要です。
例えば、会社名を変更する際は定款を変更し、その内容を登記します。事業目的についても同様で、新しい事業を始めたり、既存の事業をやめたりして定款を変更した場合は、変更登記が求められます。
会社の所在地が変わった場合も、本店移転の登記が必要です。定款に最小行政区画までしか記載していない場合、同じ区画内での移転であれば定款変更は不要ですが、登記は必要です。
役員の変更は、原則として定款変更は不要で登記のみが必要ですが、役員の人数や任期を変更する際には、定款の変更と登記の両方が必要となります。
登記の際には、申請書や株主総会の議事録など、いくつかの書類を法務局に提出します。
4. 変更定款を原始定款と一緒に保管
定款を変更したら、新しい定款「現行定款」と最初に作った定款「原始定款」と一緒に保管する必要があります。
原始定款は、会社を設立したときに作られた、会社の基本的なルールブックといえます。現行定款は、その内容やルールが変わったときに、いつ、どのように変わったのか詳細を記録したものです。ほかには、株主総会の議事録も一緒に保管します。この3つをセットで保管することで、定款がどのように変更になったのかをいつでも確認できるようになります。
また、会社を運営し、金融機関などで融資を受けるときや新たに登記を行うときに、定款の写しの提出を求められることがあります。
これらの書類は、会社の根幹である重要な情報が含まれるため、紛失しないように厳重に管理するようにしましょう。
定款変更にかかる費用

定款の変更を検討する上で、気になるのが費用面ではないでしょうか。定款変更の手続きには、大きく分けて2種類の費用が発生します。
一つは、変更した内容を法的に登録するための、法務局への登記申請にかかる費用です。これは、変更する内容によって金額が変動する場合があります。
もう一つは、手続きを専門家に依頼する場合に発生する費用です。司法書士といった専門家に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進めることができますが、その分の費用も考慮に入れる必要があります。ここでは、それぞれの費用について詳しく解説します。
・法務局への登記申請費用
先述したように、定款変更に伴い法務局へ登記申請をする際には、登録免許税がかかります。原則として、1回の申請につき3万円がかかり、変更事項が複数あっても金額は変わりません。ただし、本店の移転とほかの変更を同時に行う場合は、それぞれに登録免許税が必要となるため、合計で6万円になります。
さらに、本店をほかの法務局の管轄地域に移す場合は、旧所在地と新所在地の両方で登記申請が必要となり、それぞれ3万円ずつ、合計で6万円の登録免許税が必要です。
また、支店がある会社が商号や本店を変更する場合には、支店所在地でも登記申請が必要となり、その際には9,000円の登録免許税がかかります。
・専門家への依頼費用
この登記申請は、自分で行うことはもちろん、司法書士などの専門家に依頼することもできます。
自分で手続きをする場合は、費用を抑えることができますが、書類の準備や手続きに時間がかかります。専門家に依頼する場合は、費用は高くなりますが、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
費用相場は、会社の規模や専門家によって費用は異なりますが、おおよそ2~4万円です。
専門家に依頼するかは、費用だけでなく専門家の経験や実績、得意分野などを考慮して決めることが大切です。見積もりを取り比較検討することをおすすめします。
定款変更の注意点とは

定款を変更する場合、いくつか押さえておくべき大切なポイントがあります。
まず、定款は会社の根幹であり、一度作成された原始定款そのものを直接書き換えることはできません。変更があった場合は、新たな定款として作成し、保管する必要があります。また、変更事項によっては、法務局への登記申請に期限が設けられているため、速やかな手続きが求められます。さらに、定款の変更内容によっては、株主総会での特殊決議が必要となる場合もありますので注意が必要です。一方で、設立時の定款作成とは異なり、変更手続きにおいては公証人の認証は原則として不要となります。これらの注意点を詳しく説明します。
・原始定款を直接変更しない
定款変更を行う際、注意すべき点として、原始定款、会社設立時に作成された最初の定款そのものを直接変更してはいけないということがあります。
原始定款は、会社の設立時の基本ルールを定めたもので、法的にも重要な書類です。そのため、内容を変更する必要が生じた場合は、定款記載の事項を変更するなら別に現行定款を作成した上で、定款変更の手続きと、内容によっては株主総会の特別決議が必要です。
定款の変更には手間や経費がかかるため、初めに定款を定める際には、会社の軸となるところをきちんと定めた上で、変更がないように十分検討しましょう。
・登記申請には期限がある
法務局への登記申請には期限があることを覚えておきましょう。
会社法という法律で、定款変更の効力が発生した日から原則として2週間以内に、変更の内容を登記申請しなければならないと定められています。
具体的には、株主総会で会社の目的を変更する決議をした場合、その日から2週間以内に、変更後の目的を法務局に届け出る必要があるということです。
期日を過ぎた場合、100万円以下の過料が科される可能性があるので十分に注意しましょう。
書類を準備するのにも時間がかかる場合がありますので、株主総会が終わったらすぐに準備に取りかかり、迅速に申請を行ってください。
・株主総会の特殊決議が必要になる場合
定款を変更するには、株主総会で定款変更についての特別決議を経て、その内容を記録した議事録を作成しなければなりません。
また、定款変更では特殊決議を行うこともあります。例えば、株主ごとに異なる取り扱いをするといった内容や、全部の株式を譲渡制限とする内容が変更に含まれる場合に、特殊決議を行うことになります。特殊決議では、内容によって議決権を持つ株主の半数以上が出席した上で、3分の2以上もしくは4分の3以上が賛成することが必要です。
合同会社の場合は、定款の変更には原則として全社員による決議と承認が必要であり、社員全員の同意がなければ定款を変更することはできません。
このように、定款の変更は、会社の形態によって手続きが異なりますが、いずれの場合も慎重な手続きが必要です。
・公証人の認証は不要
株式会社は設立時に、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。しかし、設立後に定款を変更する場合には、公証人の認証や公証役場での認証手続きは不要です。
定款の変更には、事業目的の追加や変更、本店所在地の移転、商号の変更などが該当し、これらの変更は、株主総会での決議を受けて、法務局での変更登記手続きによって有効になります。
ただし、定款変更の内容によって変更登記が必要ない場合もあります。例えば、発起人の氏名の誤記を訂正する場合や、事業目的の軽度な修正などです。
これらの場合、定款の訂正で済ませることができる場合もありますが、詳細については公証役場に確認することをおすすめします。
このように、設立時とその後の変更手続きとで、必要な手続きとそうでないものが多数存在します。
内容を理解して、適切な手続きを踏むことで、スムーズな変更ができるでしょう。
まとめ
会社運営の根幹、軸となる定款変更は、会社にとって大きな転換点となる可能性を秘めています。しかし、その手続きは複雑であり、確認を行いながら着実に行いましょう。
本記事では、定款変更にかかる費用や注意点、手続きの流れについて具体的な事例なども含めて解説しました。
手続きの流れは、大きく分けて株主総会での決議と定款の変更、法務局への登記申請というステップを踏みます。それぞれのステップで必要な書類や手続きが異なるため注意が必要です。また、株主総会の特別決議が必要であることや登記申請には期限があることにも気を付けなければなりません。定款変更によって税務上の影響が生じる場合もあるため、事前に専門家に相談することも重要です。
本記事を参考にしながら、定款の手続きや必要書類、記載内容を十分検討してみましょう。