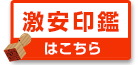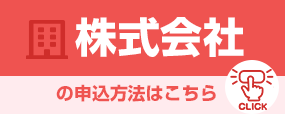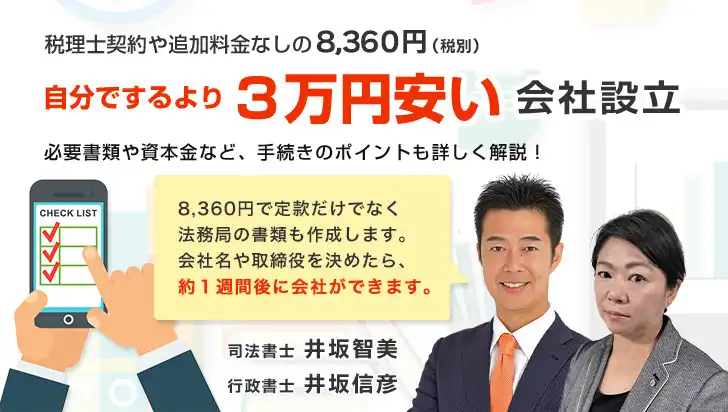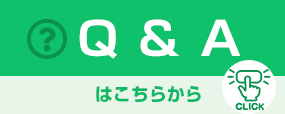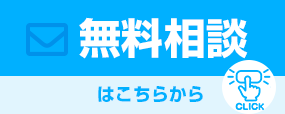合同会社とは会社形態の一種で、出資者と経営者が同じであり、かつ全員が有限責任になる形態を指します。Web上では「1日で設立可能」「3日あればいける」という記載も見られますが、実際のところはそこまで簡単な話ではなさそうです。
この記事では、合同会社についてそのようなうわさが立つ理由と、実際のところはどうなのかを手順を踏まえながら詳しく解説します。
本当に合同会社は1~3日あれば設立できるのか
合同会社は1日もしくは3日で設立できるという主張を理解するためには、まずは設立の流れを踏まえて考えてみる必要があります。ここでは、合同会社を1日もしくは3日で設立する場合の流れについて解説します。
1日で設立したい場合の流れ
まず、合同会社を設立するためには、少なくとも以下の4つのタスクをこなさなくてはいけません。
- 1.会社概要を決める
- 2.定款を作る
- 3.資本金を払い込む
- 4.法人登記申請の手続きをする
極端な話、これらのタスクを1日ですべてこなすのは不可能とまではいえません。
3日で設立したい場合の流れ
理論上、1日で合同会社の設立を完了させることはできますが、実際はもう少し時間が欲しいところです。より現実的なスケジュールにするには、以下の点を意識しましょう。
- ・1日目~2日目:会社概要、定款の詳細を詰める
- ・2日目:資本金の払い込みを済ませる
- ・3日目:法人登記申請の手続きを済ませる
不可能ではないものの、このスケジュールにも決して余裕があるとはいえません。法的に見て問題がない形で手続きを進めるのは、初めて会社を設立する人にとっては決して簡単ではないためです。
合同会社を設立するなら2週間は欲しい

実際のところ、合同会社を設立する、つまり事前準備から登記手続きに至り、登記事項証明書を発行してもらうという一連のプロセスを完成させるには、2週間は欲しいところです。1日や3日では到底終わらないと考えるほうが自然でしょう。
ここでは、合同会社を設立するためのプロセスを、具体的に行うべきこととも絡めながらより詳しく解説します。
1.会社の概要を決める
合同会社を含めて会社を設立する場合は、会社の基本事項=概要を決める必要があります。具体的には以下の項目について決めることになりますが、ほかにも必要だと思うことがあれば随時すり合わせましょう。
- ・会社名(商号)
- ・社員(出資者)
- ・事業内容
- ・出資金の額
特に、複数の人が社員になる場合は、後々もめる原因にならないよう、十分話し合いを重ねつつ決めていきましょう。
2.定款を作る
次に、定款を作成します。定款とは、会社の基本情報やルールをとりまとめた、いわば「その会社のルールブック」といえるものです。法人登記手続きのときだけでなく、税務署や自治体、銀行などの金融機関などにも提出することがあるため、しっかりと作りましょう。
なお、定款には以下のことを書く必要があります。Web上で公開されているテンプレートを使えば自分たちで作成できますが、法的に問題がないか専門家にチェックしてもらうとより確実でしょう。
| 項目 | 概要 | 具体例
|
| 絶対的記載事項 | 定款に記載しないと定款自体の効力が生じない事項 | 事業目的
商号 本店の所在地 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 社員(出資者)の氏名または名称および住所 |
| 相対的記載事項 | 決まりがあるなら記載しないと効力が生じない事項 | 持分の譲渡制限
代表社員の定め 存続期間または解散の事由 社員の加入および退社の事由 相続人等に対する売渡請求 |
| 任意的記載事項 | 社内規定などほかの方法で規定できる事項。法令、公序良俗に違反しなければ基本的に自由に決めてよい | 事業年度
業務執行社員の人数 業務執行社員の報酬 |
3.資本金を払い込む
定款をまとめたら、資本金を払い込む必要があります。資本金とは会社の設立・運営のために使う資金を指し、法人登記申請の手続きの際は、確かに資本金が払い込まれたことを証明しなくてはいけません。
この段階では会社はまだ設立前であるため、代表者の口座に払い込む必要が出てきます。社員(出資者)全員が払い終わったら、問題がないか確認しましょう。銀行などの金融機関で払込証明書を作成してもらい、通帳や利用明細の写しと一緒にまとめておいてください。
4.実印を作る
合同会社を含め、会社の設立・運営にあたっては押印が必要になる場面が度々出てきます。そのため、実印を持っていなければこのタイミングで作っておきましょう。
個人の実印のほかに、会社の代表者印や銀行印、角印も作っておくと安心です。実店舗型の印章店で作成してもらうのが一般的ですが、時間がない場合はオンラインショップを使ってもかまいません。
また、実印が出来上がったら市区町村役場で登録し、印鑑証明書を取得しておきましょう。
5.法務局に書類を出す
ここまでの準備が完了したら、本店所在地を管轄する法務局に書類を提出します。例えば、本店所在地が神戸市中央区であれば、神戸地方法務局(本局)に出向きましょう。
- ・合同会社設立登記申請書
- ・定款
- ・印鑑届出書
- ・代表社員の就任承諾書
- ・代表社員の印鑑登録証明書
- ・業務を執行する社員の一致を証する書面
- ・出資の払い込み、給付を証する書面
- ・代理人が登記申請をするなら、その権限を証する書面
- ・資本金の額が法令にのっとって計上されたことを証する書面(出資財産が金銭のみなら不要)
また、時間がない場合はオンラインで法人登記申請手続きを行ってもかまいません。必要な書類を電子ファイル形式にまとめ、電子署名を付した状態で法務局に提出しましょう。
そもそも合同会社って何?
合同会社は比較的早く設立が完了する会社形態といわれています。しかし、そもそも合同会社が何かを理解せずに進めてしまうと、後悔する結果になりかねません。ここでは、合同会社の基本的な知識について解説します。
合同会社の特徴
合同会社は、出資者と経営者が同一であることを大きな特徴とする会社形態の一種です。アメリカのLLC(Limited Liability Company、有限責任会社)をモデルにし、2006年5月1日の会社法改正により設けられた比較的新しい会社形態です。なお、インターネット通販の「Amazon」の日本法人(アマゾンジャパン合同会社)も、合同会社の形態を取っています。
なお、合同会社の社員の責任範囲は有限であるため、万が一会社が倒産しても、債権者に私財を投げ打って弁済する必要はありません。この点に関しては、株式会社における株主と共通しています。逆に、社員の責任範囲が無限である場合は、会社が倒産したときは私財を投げ打ってでも債権者に返済しなければなりません。合名会社はすべての出資者が無限責任を負うことになっています。また、合資会社では無限責任、有限責任の社員がそれぞれ最低1名以上いる仕組みです。
合同会社とほかの会社の違い
合同会社をより深く知るために、ほかの会社形態との違いについても知っておきましょう。現在の日本の法律(会社法)においては、設立できる会社の種類として、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つが認められています。
それぞれの会社の違いを簡単にまとめたので、参考にしてください。
| 項目 | 株式会社 | 合名会社 | 合資会社 | 合同会社
|
| 最低限設立に必要な人数 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 |
| 出資者の責任 | 有限 | 無限 | 無限または有限 | 有限
|
| 出資者の呼び名 | 株主 | 社員 | ||
| 最高意思決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意
|
||
| 定款の認証 | 必要 | 不要 | ||
| 決算公告の義務 | あり | なし | ||
| 株式の上場 | 可能 | 不可能 | ||
合同会社のメリットとデメリット
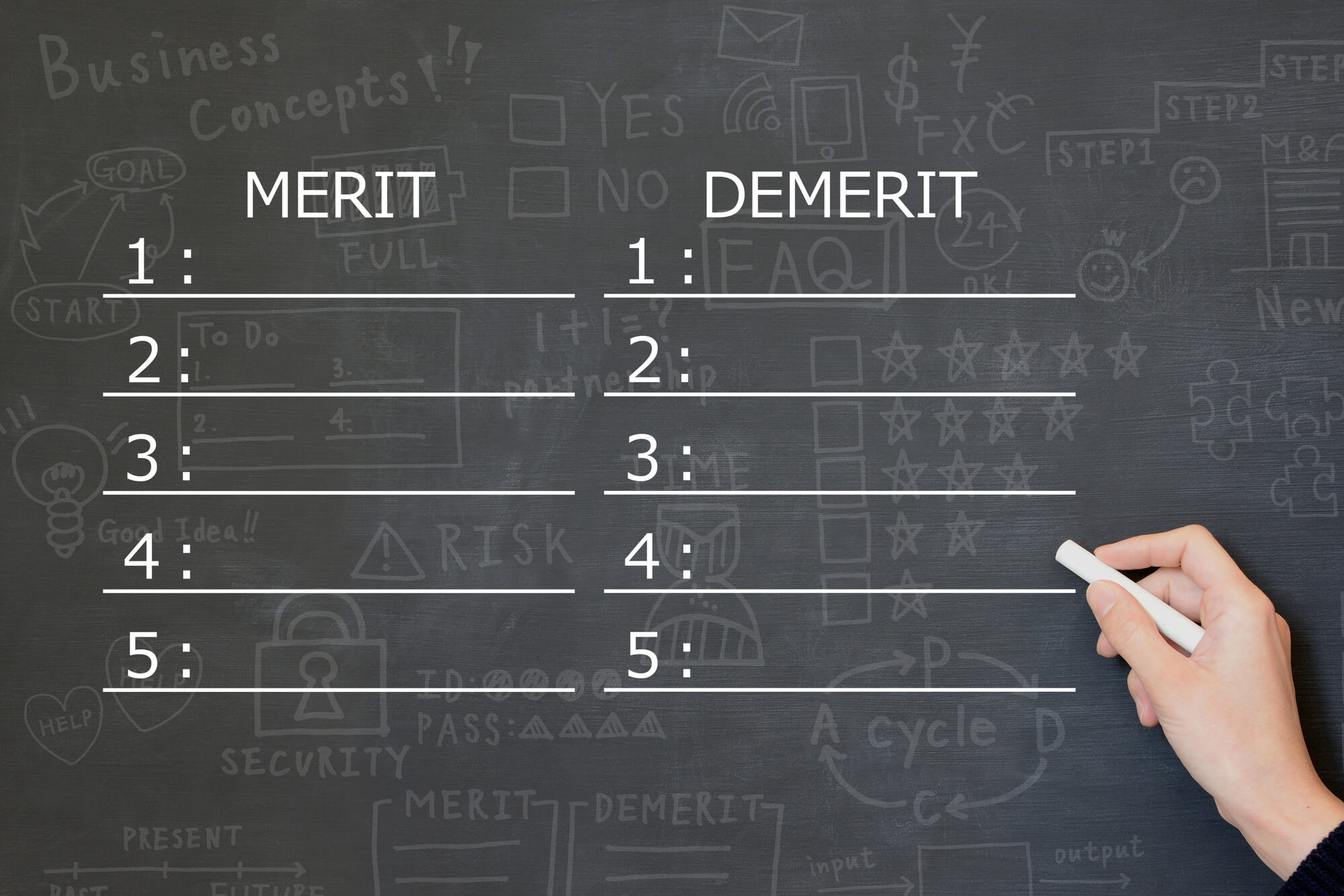
合同会社にはメリットがある一方、デメリットもあるため、両者のバランスを踏まえながら「あえて合同会社を設立すべきか」を考えるのが重要です。状況によっては、株式会社などほかの形態の会社を設立する前提で動いたほうがよいこともあります。
ここでは、具体的なメリットとデメリットについて解説した上で、適している業種についても紹介するのでぜひ参考にしてください。
合同会社のメリット
まず、合同会社のメリットとして以下の点が挙げられます。
設立費用を抑えたい場合に向いている
設立費用を抑えたいのであれば、合同会社は株式会社より優れているといえます。合同会社と株式会社の設立に際して発生する法定費用は以下のとおりです。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
| 定款用収入印紙代 | 4万円
※電子定款では不要 |
|
| 定款の謄本手数料 | 0円 | 約2,000円
(250円 / 1ページ) |
| 定款の認証料
(公証人に支払う手数料) |
なし | 5万円 |
| 登録免許税 | 6万円
または 資本金額 × 0.7% のうち高いほう |
15万円
または 資本金額 × 0.7% のうち高いほう |
| 合計 | 約10万円~
※電子定款の場合は約6万円~ |
約25万円~
※電子定款の場合は約21万円~ |
つまり、合同会社かつ電子定款を選択すれば、約6万円で会社を設立できます。一方、株式会社の場合はある程度自分でこなしたとしても、20万円以下に抑えるのは不可能です。まずはとにかく安く会社をつくりたい、というのであれば、合同会社は適しているといえます。
個人事業主と比べて節税できる
合同会社を含めた法人を設立するメリットとして、個人事業主に比べると節税につながることが挙げられます。
まず、法人であれば個人事業主として計上できる経費だけでなく、給与・賞与などの費用も経費にすることが可能です。加えて、法人が契約者となる生命保険の保険料は、一定の条件に当てはまれば全額経費として計上できます。
さらに法人としての所得が800万円超であれば、法人税率は一律23.2%となるため、個人事業主としての所得税率より低くなるかもしれません。どれだけ節税できるかは個々の事例によっても異なるため税理士に確認する必要がありますが、一定の節税効果は見込めるでしょう。
経営の自由度が高い
経営の自由度が高いのも、合同会社ならではのメリットといえます。株式会社の場合、経営に関する重要な方針・事項を決めるには、株主総会の決議にかけなければなりません。株主総会で決議にかけた結果、反対されて実現しないこともあり得ます。
しかし、合同会社では株式会社のように意思決定の場を別に設定する必要はないため、経営の自由度が高く、スピーディーな意思決定ができるのが大きな強みです。
利益の配分割合を自由に決めてよい
合同会社では、利益の配分割合も自由に決めてかまいません。出資こそしていなくても、スキルや経験があり、会社経営に貢献した人がいるのであれば、その人に対し多くの利益を配分する形にすることも可能です。
この点は、利益の配分を出資額と同じ割合にしなければならない株式会社と大きく異なります。
役員の任期は無制限
合同会社の役員の任期に制限はありません。任期が2年(非公開会社であれば10年)までと定められている株式会社とは、この点が大きく異なります。
また、株式会社ではたとえ同じ人が役員として再任された場合でも変更登記をしなくてはいけません。しかし、合同会社では同じ人が役員を続けるのであれば、変更登記は不要です。
合同会社のデメリット
一方、合同会社には以下のデメリットもあるため注意が必要です。
株式会社に比べて知名度や信頼性が低い
合同会社は株式会社とは違い、決算公告は不要です。また、家族や親族が役員に名を連ねているなど、小規模で閉鎖的な会社であることも多く、知名度や信頼性という面では不利になるかもしれません。
ただし、昨今はAmazonなどの大手有名企業であっても、会社形態として合同会社を選択しているケースもあるため、認知度も徐々に上がっているのが実情です。また、一般消費者向けの商品・サービスを主に扱うのであれば、会社形態よりも商品・サービスの質が重要になるため、大きな影響はないと考えられます。
株式による資金調達や株式市場への上場ができない
合同会社には、そもそも出資者に対する見返りとして株式を発行するというシステムがありません。そのため、第三者への新株発行による資金調達は事実上不可能です。資金を調達したければ、国や自治体の補助金、金融機関からの融資に頼ることになります。
また、株式市場への上場もできません。株式市場への上場により知名度の向上や多額の資金調達を目指すなら、どこかのタイミングで組織変更をする必要が出てきます。
合同会社が向いている業種
ここまでの内容を踏まえると、合同会社が向いている業種や人の特徴は以下のようになります。
- ・初期費用、ランニングコストを抑えて会社をつくりたい
- ・家族・親族、友人・知人など身近な人と一緒に起業する
- ・小売業、サービス業などの「BtoC」事業を営むつもりである
まとめ
合同会社は比較的短期間で設立できる形態ではあるものの、さすがに1~3日間で完了させることは現実的には難しそうです。後々トラブルにならないためにも、2週間程度はスケジュールとして見積もるとよいでしょう。
また、手掛ける業種や将来的なビジョンの観点から、あえて合同会社以外の形態を選択したほうがよいこともあります。個々の状況により最適解は異なるため、司法書士などの専門家に相談してください。
会社法人センターでは、全国最安クラスの8,360円(税込)にて設立手続きを承っております。書類、電子定款の作成は司法書士および行政書士が担当。設立後に顧問契約を結んでいただくかは、ご利用者様に決めていただいてかまいません。会社設立に際してお悩みがありましたら、まずは一度ご相談ください。