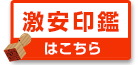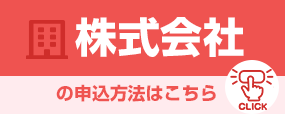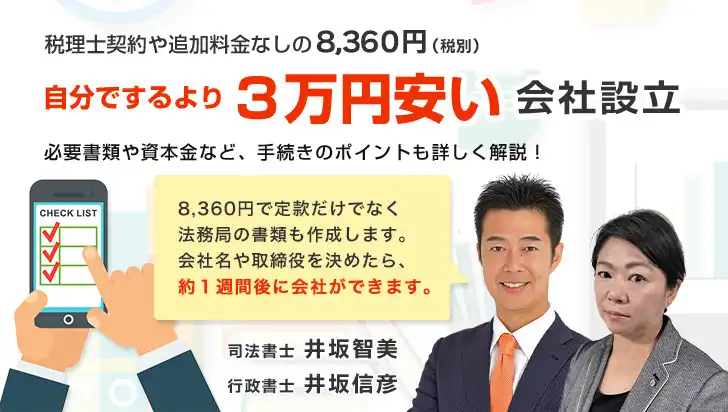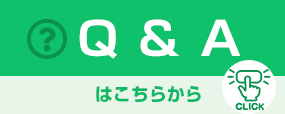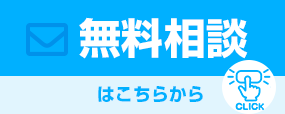会社設立は、やりたい事業や仕事を形にするための大切な第一歩です。しかし、いざ始めようとすると、「何からするべき?」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか。
本記事では、会社設立の基礎知識から具体的な手続き、設立後の準備まで、いざというときにスムーズに事業をスタートできるよう、分かりやすく丁寧に解説していきます。
株式会社と合同会社、それぞれの特徴や設立前に決めておくべきこと、煩雑に思える書類の手続きも、一つひとつひも解いていきましょう。
会社設立の基本を理解する
ここでは、会社の概念の基本を身に付けていきましょう。
株式会社とは?
会社形態の中で、現代においてもっとも一般的な形態です。「株式」を発行することで多くの人から資金を集め、その資金を元手に事業を行う会社のことを指します。
「株式会社」という名前のとおり、この会社には「株式」が存在します。株式を保有している人を「株主」と呼び、株主は会社に対して出資した金額の範囲内で責任を負います。万が一、会社が倒産した場合も、株主が個人財産を失うことはありません。
また、株式会社は利益を追求し、それを株主へと還元することを目指します。株主は、会社の業績に応じて「配当」を受け取ったり、保有する株式の価値が上がったりすることで、利益を得ることができます。
株式会社のメリット
株式会社のメリットについて、2つの視点から見ていきます。
・資金調達の選択肢が豊富(株式発行など)
株式会社の大きなメリットの一つは、資金調達の選択肢が豊富であることです。特に「株式の発行」は、その代表的な方法で、会社の一部を「株式」という形で投資家に販売し、その対価として資金を得る仕組みです。銀行からの融資とは異なり返済の義務がない資金であるため、会社の財務状況に過度な負担をかけることなく、事業拡大のための資金を調達できます。
・社会的な信用度が高い
株式会社は、ほかの会社形態と比較して社会的な信用度が非常に高いというメリットがあります。
これは、会社を設立する際に法律で定められた多くの手続きを踏む必要があるためです。決算公告の義務があり、透明性が確保されていることから、取引先や金融機関、そして一般消費者からの信頼を得やすくなります。
例えば、新規の取引を始める際や銀行から融資を受ける際、また優秀な人材を採用する上でも、安定した企業イメージは大きな後押しとなり、結果として会社の成長を見込むことも可能になります。
株式会社のデメリット
次に、デメリットやマイナスとなる部分を探ります。
・設立手続きが比較的煩雑
株式会社を設立する際のデメリットの一つとして、手続きが比較的複雑であることが挙げられます。多くの書類を作成し、さまざまな機関に提出する必要があります。例えば、会社の基本的なルールを定めた「定款」の作成や、それを公証役場で認証してもらう手続き、そして法務局での設立登記などです。
これらの手続きには、専門的な知識が必要となる場合もあり、慣れない人にとっては時間も手間もかかります。その場合は専門家への相談をおすすめします。
・設立や運営コストが高い
株式会社は設立時だけでなく、設立後の運営においてもコストがかかるという点もデメリットといえるでしょう。まず設立時には、登録免許税や定款の認証手数料など、少なくとも20万円程度の初期費用が必要です。さらに、会社を運営していく上でも税理士への報酬や社会保険料の負担、会社の規模によっては監査費用なども発生します。また、利益が出た場合には、法人税や法人住民税、法人事業税といった税金が課されます。
・株主総会などの機関設計が必要
株主総会や取締役会といった「機関」の設置が義務付けられている点もデメリットとなります。
機関設計が必要なのは、会社を運営していく上での重要な意思決定を、これらの機関で行う必要があるためです。特に株主総会は、年に1回は必ず開催し、事業報告や役員の選任など、法律で定められた事項を決定しなければなりません。また、取締役会を設置する場合は、取締役の人数など一定の要件を満たす必要があるなど、複雑な手続きが増えます。
合同会社とは
合同会社は、社員・出資者全員が会社の経営に直接関わることができるという特徴を持つ会社です。株式会社のように株式を発行するのではなく、出資者全員が「社員」という形で会社に携わります。
また、出資した金額の範囲内で責任を負う「有限責任」であるため、万が一会社がうまくいかなくなっても、個人の財産が守られるという点で、株式会社と同じように安心感があります。小規模な事業や、特定のメンバーが共同で事業を行う場合に特に適しているといえるでしょう。
合同会社のメリット
合同会社のメリットについて、株式会社との違いなども含めて詳しく解説します。
・設立手続きが比較的簡単で費用が安い
手続きが比較的簡単で、費用も安く済むことは大きなメリットです。
株式会社の場合に必要な「定款の認証」などの手続きが不要なため、その分の手間と費用を省くことができます。また、株式会社に比べて登録免許税などの法定費用が安く、全体的な設立費用を抑えることが可能です。これは、開業資金をできるだけ抑えたい人にとっては大きなメリットといえるでしょう。
・社員の責任範囲が有限責任
合同会社は、出資者である「社員」全員の責任範囲が「有限責任」であるという大きなメリットがあります。これは、会社が倒産したり、多額の負債を抱えたりした場合でも、出資した金額の範囲内でしか責任を負う必要がない、という意味です。
個人の財産を会社の借金の返済に充てる必要がないため、安心して事業に挑戦することができます。
・利益配分や組織運営を自由に設計しやすい
利益の配分方法や組織の運営方法について、自由度が高い点も大きな特徴といえます。株式会社のように出資額に応じて利益を配分する義務がなく、どのように利益を分けるかを自由に定めることができます。
例えば、出資額に関わらず、会社の貢献度に応じて利益を配分するといった柔軟な対応が可能です。また社員間の合意があれば、業務の役割分担や意思決定の方法なども自由に設定できるため、少人数で共同事業を行う場合に、それぞれの働き方や貢献度に応じた柔軟な体制を築きやすいといえます。
合同会社のデメリット
同様にデメリットについても考えてみましょう。
・株式会社に比べて社会的な信用度が低い場合がある
株式会社のような厳格な設立手続きや情報公開の義務がないため、一部の取引先や金融機関から事業規模が小さい、あるいは信頼性に欠けるといった印象を持たれる可能性があります。特に、大規模な取引や銀行からの融資を検討する際には、株式会社と比較して不利になるケースも考えられます。
・資金調達の選択肢が限られる場合がある
株式会社のように株式を発行して広く投資家から資金を集めるという方法ができないため、資金調達は主に銀行からの借り入れや社員自身の出資に頼ることになります。
将来的に大きな事業展開を考えている場合や、多額の資金を必要とするビジネスを検討している場合は、この点が足かせとなる可能性があります。
設立前に決めておくべきこと

ここで、会社を設立する前に決めておきたい内容について、項目ごとに詳しく解説します。
会社名(商号)
会社の顔となる会社名(商号)は、事業を行う上でのブランドイメージを左右する重要な要素です。同じ住所ですでに登記されている会社名や、誤解を招くような名称は避ける必要があります。インターネット検索や法務局のデータベースで事前に調査し、商標権侵害にも注意しましょう。
事業目的
会社がどのような事業を行うのかを示すのが事業目的です。これは、会社の定款に記載される重要な項目で、将来的に事業を拡大する可能性も考慮して具体的に定めます。例えば、「飲食店の経営」だけでなく、「食料品の販売」なども含めることで、将来の事業展開に対応できます。
本店の所在地
本店の所在地も決定事項の一つです。会社の登記簿に記載され、税務署などからの書類が送付される住所となります。自宅を本店とする場合は、賃貸契約の内容を確認したりバーチャルオフィスを利用したりと、自身の状況に合わせて選択肢を検討しましょう。
資本金
資本金は、会社設立時に出資する金額で、会社の事業活動の元手となります。法的な最低金額はありませんが、会社の信用力や、当面の運転資金を考慮して決めることが重要です。金融機関からの融資や取引の際、資本金の額が信用の一つの目安となることもあります。
決算期
決算期とは、事業年度の最終月のことです。年に一度、会社の財政状態や経営成績を確定する期間となります。決算期は自由に設定できますが、消費税の免税期間を考慮するなど会社の事業内容や運営のしやすさに合わせて決めるのが一般的です。
役員構成
株式会社の場合、誰が役員になるのか、代表取締役や取締役なども事前に決める必要があります。合同会社の場合は、「社員」として経営に携わるメンバーを確定します。
設立手続きと必要な書類とは
会社設立にはいくつかの段階があり、それぞれで必要な書類を用意します。
まず、会社の基本的なルールを定めた定款の作成が必要です。これは会社の憲法ともいえる重要な書類で、事業目的や会社名などを記載します。次に、作成した定款が法的に正しいものであることを公証役場で証明してもらう定款の認証という手続きを行います。その後、設立時に必要となる資本金の払い込みを行います。これらの準備が整ったら、最後に会社の設立を法的に登録するための設立登記の申請を法務局で行うことで、会社を設立できます。
必要な書類
登記申請書
登記申請書は、会社設立の登記を申請するためのもっとも重要な書類です。会社の商号、本店所在地、設立の目的、資本金の額、役員の氏名や住所など、会社の基本的な情報を記載します。法務局が提供する申請書の様式を正確に用いて、会社の情報を漏れなく記載します。会社の商号、本店所在地、事業目的などは、その後の事業活動に大きく影響するため、慎重に決定し誤りがないように記載してください。申請書には、会社の代表者が署名し、実印を押印します。
定款
定款は、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた、会社の根幹になる重要な書類です。会社の商号、事業目的、本店所在地、設立の方法、役員に関する事項、会計に関する事項などを記載します。定款には、法律で定められた絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項を記載する必要があります。その後、株式会社の場合は公証人の認証を受ける必要があります。
発起人の決定書
発起人の決定書は、定款に記載していない重要な事項について、発起人が同意した上で決定されたことを記載したものです。商号や本店所在地、設立時役員の選任、資本金の額などが、定款に記載されていない場合に作成します。発起人が複数いる場合は、全員が署名押印します。決定事項は、定款の内容と矛盾がないように記載してください。
取締役の就任承諾書
設立時取締役の就任承諾書は、会社の設立時に取締役に就任する人が、その役職に就くことを承諾する意思を示す書類です。選任された株主総会の日付、就任する取締役の氏名・住所などを正確に記載した上で、本人が署名捺印してください。
監査役の就任承諾書(必要な場合)
監査役を置かない場合には作成が不要です。必要な場合、監査役は株主総会の決議により選任されます。就任承諾書に記載すべき事項と同様、選任された株主総会の日付、選任された役職名、役職に就任することを承諾する旨、作成日、役員の氏名・住所を記載してください。
印鑑届出書
印鑑届出書は、設立する会社の代表者印(会社実印)を法務局に登録するための書類です。会社設立後、契約書への押印やさまざまな手続きなどで使用する重要な印鑑となります。
登録する印鑑の印影を鮮明に押印し、会社の商号、本店所在地、代表者の氏名・住所などを正確に記載してください。
払込証明書
払込証明書は、発起人が出資した資本金が会社の口座に正しく払い込まれたことを証明する書類です。口座への払込を証明する書類として、通常は通帳のコピー(表紙、個人情報欄、資本金の払込が記載されたページ)をとじて提出します。
印鑑証明書
印鑑証明書は、取締役に就任する人の個人の実印が市区町村に登録されているものであることを証明する公的な書類です。発行から3カ月以内のものを提出する必要があります。取締役全員または、取締役会を設置している場合は代表取締役に就任する人の印鑑証明書が必要です。
登録免許税納付用台紙
登録免許税は、設立登記の際に資本金額に応じて納付する必要がある税金です。現金ではなく、郵便局か法務局で収入印紙を購入して、登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
株式会社と合同会社で金額の算出方法が異なり、株式会社は「資本金の額 × 0.7%または150,000円」のどちらか高いほう、合同会社は「資本金の額 × 0.7%または60,000円」のどちらか高いほうとなります。
設立後の手続きとは

会社設立後にも多くの届出や手続きがあります。内容を確認し、迅速に行いましょう。
税務署への届け出
会社を設立したら、税務署へ必要な書類を提出する必要があります。これらは、会社の税金に関わる重要な手続きです。
法人設立届出書
会社を設立したことを税務署に知らせるための書類で、会社の基本情報(会社名、所在地、事業目的など)を記載し、設立後速やかに提出する必要があります。これにより、法人税などの納税義務が発生します。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けるための書類です。青色申告には、税金面でさまざまなメリット(例えば、赤字の繰り越しや特別控除など)があるため、多くの会社が利用しています。原則として、会社設立日から3カ月以内に提出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書
この届出をすることで、会社が給与を支払う「事務所」として認められ、従業員の源泉徴収(給与から所得税などを天引きすること)を行う義務が生じます。従業員を雇う場合は、忘れずに提出しましょう。
都道府県税事務所・市区町村役場への届け出
会社を設立したら、税務署への届け出と同様に、都道府県税事務所や市区町村役場へも法人設立届出書を提出する必要があります。
これは、法人事業税や法人住民税といった地方税の納税義務を発生させるための手続きです。提出期限は自治体によって異なりますが、一般的には会社設立後1~2カ月以内とされています。会社の登記事項証明書や定款のコピーなどを添付する場合があります。
社会保険関連の手続き
会社を設立し、従業員を雇い入れる場合は、社会保険に関するさまざまな手続きが必要となります。これらは、従業員の福利厚生と会社の義務に関わる重要な手続きです。
健康保険
従業員が病気やケガをした際に、医療費の補助を受けることができる制度です。会社が法人として設立され、従業員を5人以上雇用する場合、原則として健康保険への加入が義務付けられています。健康保険の手続きは、年金事務所で行い、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを提出します。
厚生年金保険
厚生年金保険は、将来の年金給付に関わる重要な制度で、健康保険と同様に法人を設立して従業員を5人以上雇用する場合は、厚生年金保険への加入が義務付けられています。この手続きも、健康保険と併せて年金事務所で行い、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
雇用保険
従業員が失業した場合や育児休業・介護休業を取得した場合に給付を行う制度です。従業員を1人でも雇用する場合は、原則として雇用保険への加入が義務付けられています。この手続きは、会社の所在地を管轄するハローワークで行い「雇用保険適用事業所設置届」などを提出します。
許認可の取得
事業内容によっては特定の許認可が必要となる場合があります。
許認可が必要となる場合
特定の事業を行うには、国や地方自治体からの許認可が必要です。例えば、飲食店営業や建設業など、事業内容によっては許可が必要です。無許可での事業は罰則の対象となるため、事前に確認し、必要な手続きを行いましょう。
そのほかの準備
会社設立後には、事業を円滑に進めるためのさまざまな準備が重要です。具体的には、会社の顔となるホームページ作成や、業務を行うためのオフィス準備、そして事業を支える人材採用など多くの事柄を計画的に進める必要があります。
これらは会社の成長に大きく影響するものであり、設立初期から積極的に取り組むことで、事業をスムーズに展開することができます。
知っておくと役立つこと
会社設立後も、事業をスムーズに進めるためにはさまざまな知識が必要になります。
法務や税務に関することなどについて学ぶこと、専門的な内容は行政書士や弁護士などの相談先を考えておくことが重要です。
また、事業に必要な資金調達の方法として融資、補助金・助成金、投資など、さまざまな資金調達の方法を検討し、計画的に進めることも念頭に置いておくべきでしょう。
さらに、ネットワークの構築を通じて、仲間や事業を成功させている先輩経営者とのつながり、セミナーの活用などを図ることで、貴重な情報や支援を得ることも経営者としての力や人間力を育みます。これらは、会社の安定的な成長につなげるための先行投資として考えておきましょう。
まとめ
会社設立は、事業開始の重要な一歩です。株式会社と合同会社という異なる形態があり、それぞれにメリットとデメリットがありますので、将来の事業の計画に合わせてどちらの形態が適しているかを検討しましょう。
設立前には、会社名、事業の内容、会社の住所、資本金の額、会計年度、役員など、基本的な情報を決める必要があります。設立の手続きとしては、会社の根幹となる定款を作成し、認証を受け、資本金を払い込み、法務局で登記申請を行います。この際、さまざまな書類が必要になりますので、確認をしながら準備を行ってください。
設立後も、税務署や自治体への届け出、従業員がいれば社会保険の手続き、事業に必要な許可や免許の取得など数多くの手続きがあります。また、事業をスムーズに進めるためには、オフィス準備などの実務的な準備も重要になってきます。
これらの手続きや準備を進めるにあたっては、専門家のサポートを受けるのもよいでしょう。
会社法人センターは、煩雑な会社設立の手続きを全国最安の8,360円(税込)で代行いたします。司法書士と行政書士が書類や電子定款、登記後の書類まですべて作成します。設立後の顧問契約の強制などはございませんので、安心してご依頼ください。