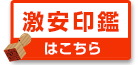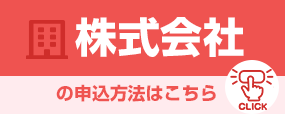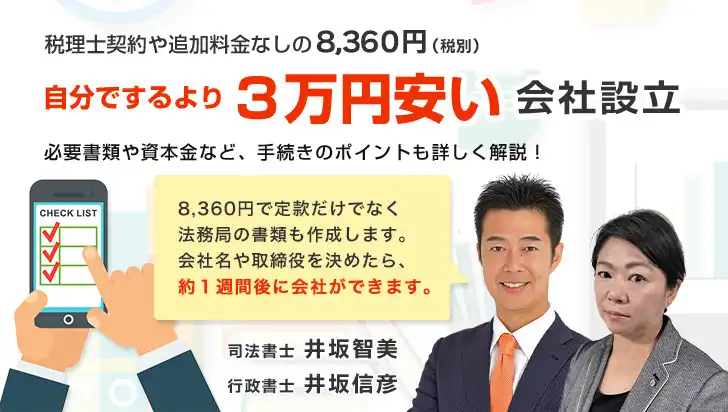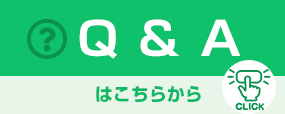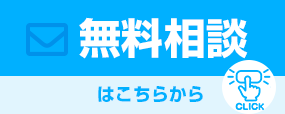起業を検討したり、会社を設立したりする際に必ずぶつかるのが「合同会社」と「株式会社」の選択です。どちらを選ぶべきか迷いますよね。それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、自社の事業に最適な事業形態を選ぶことが企業を成功させる第一歩となります。
本記事では、合同会社と株式会社の違いを分かりやすく解説し、最適な事業形態を選ぶためのヒントを提供します。
合同会社と株式会社の違いとは?
まず、どちらを設立すべきか考えるにあたって、両者の違いを正確に理解しておくことが非常に重要です。
ここでは、合同会社と株式会社の違いについて詳しく解説します。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社
|
| 会社の所有者
|
株主 | 社員(出資者) |
| 経営を行う人 | 所有者と異なるケースもある | 所有者と同じ
|
| 意思決定 | 株主総会 | 全社員の同意
|
| 株式市場への上場 | 可能 | 不可
|
| 会社の代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
合同会社とは
合同会社は持分会社の一種で、資本金を出資する有限責任社員のみで構成されているのが大きな特徴です。経営に関する権限は出資者である社員が持つため、出資者は「社員かつ経営者」という立場に立たされます。このことを「所有と経営が一致している」と表現するケースもあるため、覚えておきましょう。また、株式会社では経営を取り締まるトップの役職として「代表取締役」が設けられていますが、合同会社では「代表社員」と呼ばれます。
ちなみに、合同会社はアメリカにおける有限責任会社(LLC:Limited Liability Company)をモデルにして2006年に導入された比較的新しい会社形態です。
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行し、出資者に見返りとして交付することで資金を集めて事業を運営していく会社形態の一種です。利益が出れば持分に応じて分配=配当を行うこともありますが、あえて行わずそれを原資に再投資をすることもあります。
出資の単位が株式となっているため、比較的多数の投資家から出資を募ることが可能です。また、合同会社とは異なり所有と経営は分離されています。つまり、株主が自ら経営に携わるのではなく、株主総会で適した人物を選定して経営を任せる仕組みです。ただし、中小企業では株主が自ら経営に携わることも多くなっています。
なお、株式会社の株主および合同会社の出資者はいずれも有限責任を負う仕組みです。つまり、会社が倒産してしまった場合でも、原則として会社の債権者に対して出資額以上の責任は負いません。つまり、会社として負っていた債務について、出資額を超えて返済する必要はないと考えましょう。
合同会社と株式会社のメリットとデメリット
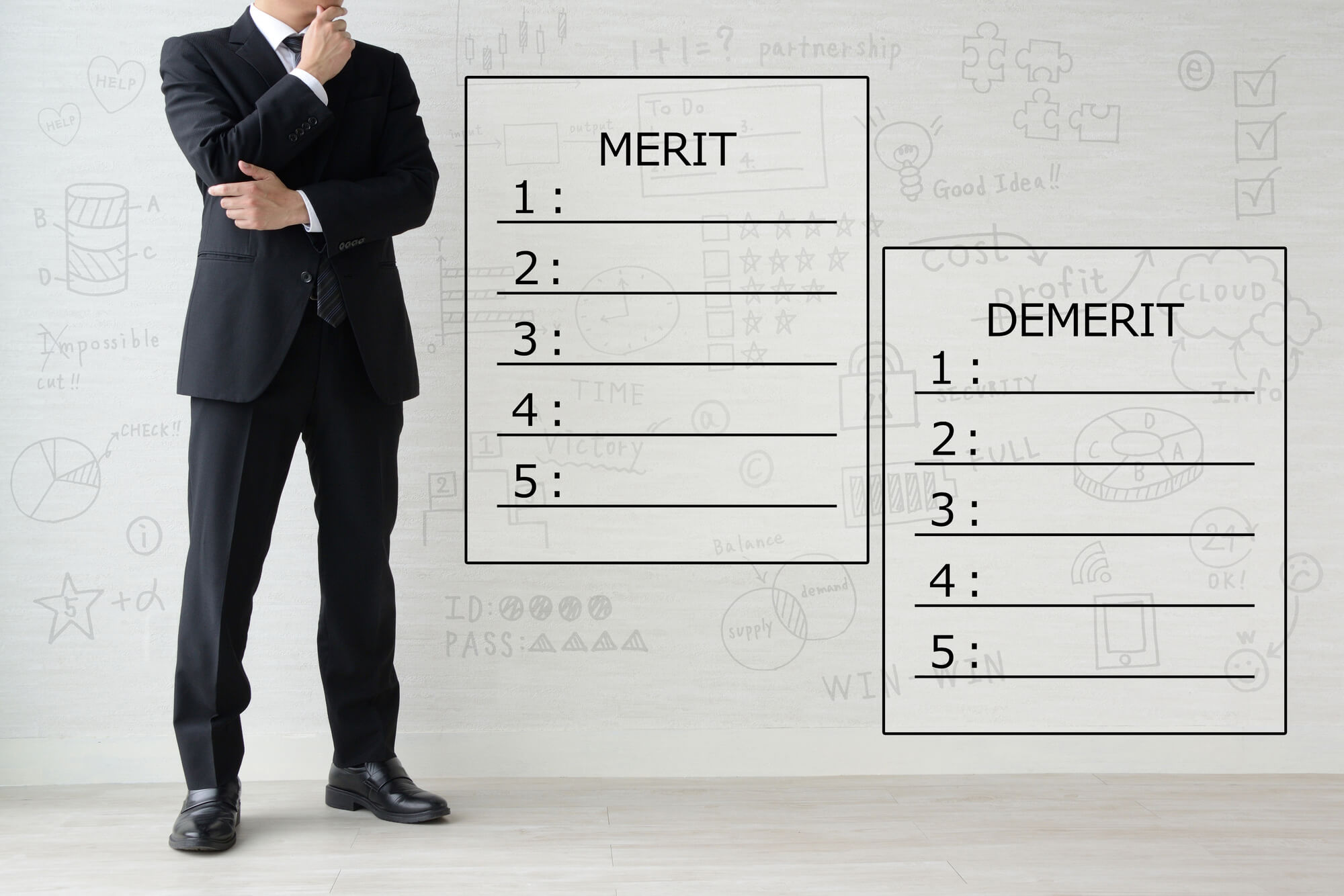
合同会社と株式会社にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どちらを設立するべきか、その人が置かれた状況によっても異なるため一概にはいえません。
ここでは、合同会社と株式会社について、メリットとデメリットを詳しく解説します。
合同会社のメリット
まず、合同会社のメリットは以下の3点です。
- 1.出資者は有限責任しか負わない
- 2.法人格を安い設立費用で持てる
- 3.自由度の高い経営が行える
出資者は有限責任しか負わない
合同会社の1つ目のメリットとして挙げられるのは「出資者は有限責任しか負わない」ことです。前述したように、合同会社の出資者は、会社の債権者に対し有限責任を負うに過ぎません。つまり、自分が出資した額以上の責任を負わされることは原則としてない仕組みになっています。合資会社や合名会社の出資者のように、会社が倒産した場合に私財で補填してでも会社の債務者に返済する必要はありません。
ただし、実際は合同会社が融資を受ける際、代表社員が連帯保証人になることも多く、倒産したら個人として責任を取る必要があります。
法人格を安い設立費用で持てる
2つ目の合同会社のメリットとして挙げられるのは「法人格を安い設立費用で持てる」ことです。合同会社でも株式会社と同様、定款を作成する必要があります。しかし、公証役場での定款の認証は、合同会社の場合は不要です。その分の手数料=認証手数料がかからないため、合同会社は株式会社に比べると安い費用で設立できます。
なお、合同会社の設立にあたってかかる費用は資本金の額によって異なりますが、もっとも安いパターンの場合は6万円で設立することが可能です。
| 定款
|
4万円(書面発行)もしくは0円(電子定款) |
| 登録免許税
|
資本金の0.7%相当額
※6万円未満の場合は6万円 |
自由度の高い経営が行える
3つ目の合同会社のメリットとして挙げられるのは「自由度の高い経営が行える」ことです。合同会社は出資と経営が一致しているため、定款の範囲内であれば比較的自由に経営できます。株式会社のように、重要事項を株主総会決議にかけたものの拒否されて実行に至らない、ということはあり得ません。
また、株式会社に比べると定款の自由度も高くなっています。例えば、会社の実情に合わせて、以下の工夫を盛り込むことも可能です。
- ・出資比率に合わせて議決権に差をつける
- ・一部の社員だけが経営に参画する形を取る
- ・利益の分配比率を任意に決める
合同会社のデメリット
一方、合同会社には以下のデメリットもあることに注意しなくてはいけません。
- 1.資金調達に苦慮するおそれがある
- 2.信頼性は株式会社に劣る
- 3.上場できない
資金調達に苦慮するおそれがある
1つ目の合同会社のデメリットとして挙げられるのは「資金調達に苦慮するおそれがある」ことです。合同会社ではそもそも株式を発行しない以上、第三者割当増資(特定の第三者に有償で新しい株式を発行すること)もできません。そのため、利用できる資金調達方法が以下のものに限られることから、十分な資金調達ができない可能性もあります。
- ・社債の発行
- ・金融機関からの融資
- ・補助金や助成金の利用
信頼性は株式会社に劣る
2つ目の合同会社のデメリットとして挙げられるのは「信頼性は株式会社に劣る」ことです。
株式会社では出資者かつ会社の実質的な所有者である株主が、経営陣の行動に問題がないかを常に監視しています。そのため、ある程度は法令・モラルに反した行動を抑止することは可能です。
一方、合同会社は出資と経営が分離していないことから、監視されることもありません。法令・モラルに反した行動が行われていても抑止されずに放置され、重大な事件・事故につながる可能性もあります。
もちろん、法令・モラルを遵守し、社会に貢献して信頼されている合同会社も多数ありますが、このような可能性もあることからどうしても信頼性が株式会社よりも劣る点は意識しましょう。
上場できない
3つ目の合同会社のデメリットとして挙げられるのは「上場ができない」ことです。そもそも、株式を発行していない以上、証券取引所への上場もあり得ません。
将来的に出資者を増やすべく上場を考えているなら、どこかのタイミングで株式会社への組織変更をする必要が出てきます。ただし、組織変更計画を作成した上で、総社員の同意と債権者保護手続きを済ますなど、さまざまな手続きをしなくてはいけません。時間も費用もかかるため、上場を考えているなら最初から株式会社を設立したほうが結果としてよいケースも考えられます。
株式会社のメリット
株式会社のメリットとして挙げられるのは以下の3点であるため、以降において詳しく解説します。
- 1.株式上場ができる
- 2.合同会社よりも信頼、知名度が高い
- 3.株を発行して資金調達ができる
株式上場ができる
1つ目の株式会社のメリットとして挙げられるのは「株式上場ができる」ことです。企業が発行する株式は証券取引所に上場することで、誰でも自由に売買できるようになります。結果として、円滑な資金調達ができる上に、社会的信用や知名度をアップさせることが可能です。
ただし、上場するためには厳しい条件を満たさないといけない上に、無事に上場できてもその条件を維持し続けないといけません。また、誰でも自由に売買できる反面、企業にとって好ましくない相手に株を買い占められる(敵対的買収)リスクも出てきます。
さらに、上場を維持し続けるためには年間上場料や監査法人への報酬、株主事務代行手数料などで数千万円にものぼる費用が発生する点にも注意しなくてはいけません。情報開示体制の整備や株主対応も必要になるため、その点を踏まえて上場すべきかを考える必要があるでしょう。
合同会社よりも信頼性と知名度が高い
2つ目の株式会社のメリットとして挙げられるのは「合同会社よりも信頼性と知名度が高い」ことです。法務省「2023年度 登記統計」によれば、2023年度に設立された株式会社の数は100,669件だったのに対し、合同会社の数は40,751件に過ぎません。
つまり、会社を設立する場合、株式会社が選ばれることが圧倒的に多くなっています。合同会社という言葉を知らない人は一定数いるかもしれませんが、株式会社という言葉を知らない人はそれよりもはるかに少ないはずです。
また、株式会社を設立する際は公証役場で定款の認証を受けなくてはいけない以上、ある程度の信頼性も担保されます。このような背景を踏まえると、株式会社は合同会社に比べ信頼性、知名度が高いといえるでしょう。
株を発行して資金調達できる
3つ目の株式会社のメリットとして挙げられるのは「株を発行して資金調達できる」ことです。前述したように、合同会社では株式の第三者割当増資による資金調達ができません。しかし、株式会社ではできるため、資金調達の選択肢が合同会社に比べて多様といえます。
株式会社のデメリット
一方、株式会社には以下のデメリットがあるため注意が必要です。
- 1.出資額に応じて利益配分を決定する
- 2.設立にかかる費用や手続きが多くなる
- 3.決算公告の義務と掲載料が発生する
出資額に応じて利益配分を決定する
1つ目の株式会社のデメリットとして挙げられるのは「出資額に応じて利益配分が決定する」ことです。
つまり、たとえ貢献度の大きい出資者がいたとしても、出資額が少なければそれに応じた利益配分しか受け取れません。合同会社のように利益配分の比率を自由に決められない点に注意する必要があります。
設立にかかる費用や手続きが多い
2つ目の株式会社のデメリットとして挙げられるのは、合同会社に比べて「設立にかかる費用や手続きが多くなる」ことです。
例えば、定款一つとっても、合同会社では公証役場での認証が不要であるのに対し、株式会社では認証を受けなくてはいけません。それに伴い、認証手数料が1.5~5万円かかります。また、登録免許税も合同会社(最低6万円)に比べ、株式会社では格段に高い(最低15万円)点に注意しなくてはいけません。費用の安さだけを重視するなら、合同会社のほうが有利です。
決算公告の義務と掲載料が発生する
3つ目の株式会社のデメリットとして挙げられるのは「決算公告の義務と掲載料が発生する」ことです。
株式会社は、たとえ非上場であっても定時株主総会が終結次第遅滞なく、決算公告を行わなくてはいけません(会社法440条第1項)。つまり、官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれかに貸借対照表(大会社では損益計算書も)を中心とした一定の事項を掲載する必要があります。
なお、決算公告を官報に掲載する場合の費用は資本金の額や株式の譲渡制限の有無によって異なりますが、8~16万円程度かかると考えましょう。
会社の形態を決めるポイント

ここまでの内容を踏まえつつ、合同会社と株式会社のどちらを設立すべきか、ポイントについて触れておきます。
会社形態の選択は事業の成功を左右する重要な要素となるため、自身の考える事業内容と規模を基準に選ぶことが重要です。
また、現在の手元資金額を踏まえた上で、自由な資金調達ができるかも加味して会社形態を選ぶことも必要になります。
さらに、経営の自由度や将来得たい社会的な信頼性も考えて、合同会社と株式会社のどちらにすべきかを考えましょう。
これらの点を踏まえ、合同会社が向いている人・株式会社が向いている人の特徴をまとめましたので参考にしてください。
合同会社が向いている人
まず、合同会社が向いている人の特徴は以下のとおりです。
- 1.小規模事業を始める人
- 2.スタートアップ企業の起業家
- 3.法人化を検討している個人事業主
- 4.複数の個人が共同で事業を始める場合
- 5.専門性の高いサービスを提供する人
株式会社が向いている人
一方、株式会社が向いている人の特徴は以下のとおりです。
- 1.大規模な事業を目指す人
- 2.社会的な信用を重視する人
- 3.リスクを分散したい人
- 4.将来、株式を公開したい人
まとめ
合同会社と株式会社は、設立目的や規模や将来の展望などによってそれぞれメリット、デメリットや特徴が異なります。どちらの会社形態を選ぶべきか迷っている場合は、自身の事業や将来の展望に合ったものなのか、本記事を参考に検討してみてください。まずは、自身の事業計画を明確にし、最適な形態を考えてみましょう。
会社設立をお考えの方は、全国最安の8,360円(税込)で司法書士と行政書士が会社設立の手続きを代行する「会社法人センター」をぜひご利用ください。
公証役場に払う定款認証手数料や、法務局に払う登録免許税以外に追加手数料は一切なく、電子定款で提出するため4万円の印紙代も節約できます。会社設立代行サービスでありがちな顧問契約の強制もありませんので、安心してご依頼いただけます。